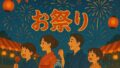エアコン2027年問題とは、2027年度から適用される新しい省エネ基準によって、今のエアコンの多くが市場から消え、価格が大幅に上がると予想される非常に重要なテーマです。
今のうちに知っておきたい「エアコン2027年問題」の全容や、これから家庭にどんな影響が出るのか、そして損しないための賢いエアコン選びや買い替えタイミングまで、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、急な出費や不安を防ぎ、家計と環境にやさしい選択ができるようになります。
ぜひ最後までチェックしてみてください。
エアコン2027年問題とは?今知っておきたい最新動向
エアコン2027年問題とは?今知っておきたい最新動向について解説します。
それでは、エアコン2027年問題の全体像から詳しく見ていきましょう。
①エアコン2027年問題の概要
エアコン2027年問題とは、2027年度から家庭用エアコンの省エネ基準が大きく見直されることにより、多くの家庭やメーカー、市場全体に影響を与える問題です。
具体的には、経済産業省が定めた新しい省エネ基準をクリアできないエアコンは、製造や販売が一切できなくなります。
この基準改定は約15年ぶりの大規模なものであり、すでに販売されているモデルの約7割が新基準を満たしていないといわれています。
つまり、今まで手頃な価格で買えていたエアコンが大幅に減少し、買い替え時の負担や家計に影響を及ぼす可能性が高まる、というのがエアコン2027年問題の本質です。
こうした動きの背景には、日本全体のエネルギー政策や、家庭の電力消費におけるエアコンの割合の高さがあるため、今後の生活に直結する重要なテーマといえるでしょう。
②なぜ省エネ基準が改定されるのか
なぜここまで大きな省エネ基準の見直しが行われるのでしょうか。
その大きな理由は、日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル目標」にあります。
カーボンニュートラルの達成には、各家庭の電力消費を効率化することが不可欠であり、中でもエアコンは家庭の消費電力全体の約25%を占めているため、エアコンの省エネ化は大きなカギとされているのです。
また、冷媒ガス(フロンガス)削減の国際的な流れも背景にあり、日本も国際社会のルールや要請に応じて基準を引き上げています。
つまり、環境負荷を減らし、世界的な持続可能社会の実現に向けて、日本のエアコン政策も抜本的に変わろうとしているのです。
③APFとは何か?その重要性
2027年問題の大きなポイントとなるのが、「APF(通年エネルギー消費効率)」という指標です。
APFは、1年間を通じてエアコンがどれくらい効率よく冷暖房できるかを示すもので、いわば「エアコンの燃費」のような数値です。
このAPFの値が高いほど、省エネ性能が高いエアコンといえます。
例えば、現行の6畳用エアコンではAPF5.8が基準でしたが、2027年からはAPF6.6へと引き上げられます。
リビング用の大型モデルではさらに厳しくなり、4.0kWクラスはAPF4.9から6.6へと、およそ35%も性能アップが求められています。
④2050年カーボンニュートラルとの関係
なぜここまで省エネに厳しい基準が求められるのかというと、日本が掲げる「2050年カーボンニュートラル」目標の達成が背景にあります。
2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにするには、家庭レベルでのエネルギー効率向上が不可欠です。
エアコンは冷暖房の主役であり、古いモデルをそのまま使い続けると、省エネ化の足かせになってしまいます。
世界中で温暖化対策が進む中、日本も「省エネ家電」の基準強化を進め、より環境にやさしい社会を目指しています。
エアコン2027年問題は、まさにこの流れの象徴といえるでしょう。
エアコンの新省エネ基準で何がどう変わる?
エアコンの新省エネ基準で何がどう変わるのかを詳しく解説します。
この章では、2027年に向けて実際にどんな変化があるのかを一つずつ見ていきましょう。
①APF基準の具体的な引き上げ内容
エアコンの省エネ基準で最も注目すべきは、APF(通年エネルギー消費効率)の数値が大幅に引き上げられる点です。
例えば、6畳用エアコンでは現在の基準APF5.8から2027年度以降はAPF6.6に、リビングなどでよく使われる4.0kWクラスではAPF4.9からAPF6.6へと、かなり高い性能が求められるようになります。
この数値アップは、単純に見えて実は技術的にも大きなハードルで、メーカー各社は冷媒回路や圧縮機、熱交換器など、基本的な構造から見直しが必要です。
また、「省エネマーク」も新しくなり、基準達成機種には緑色、未達成にはオレンジ色の表示がなされます。
これからエアコンを買う人は、マークの色にもぜひ注目してみてください。
②現行モデルと新基準モデルの違い
新基準のエアコンと現行モデルでは、どんな違いが生まれるのでしょうか。
まず最大の違いは、省エネ性能が格段にアップすることです。
メーカーは新基準を満たすために、「高性能コンプレッサー」や「大型の熱交換器」、「断熱材の品質アップ」など、従来よりも高性能なパーツを採用することになります。
さらに「AI制御」などの先進機能も標準搭載が進み、より賢く自動で省エネ運転をしてくれるようになります。
その一方で、コスト増の影響も大きくなり、これまでのような「安いけど省エネ性が低いモデル」は市場から姿を消していく可能性が高いです。
③メーカーや市場への影響
エアコン新基準の導入は、メーカー各社にとって大きな挑戦となります。
技術開発や製造ラインの見直し、品質検査体制の強化など、多くの追加投資が求められるため、開発コストや生産コストが今より格段に上がると見込まれています。
また、現在市場にある約7割のエアコンは新基準に適合しないため、2027年以降は「ラインナップが一気に絞られる」ことになります。
安価な普及モデルの販売中止や値上げだけでなく、一時的な品薄や納期遅れなど、流通全体にも大きな混乱が予想されます。
結果として、エアコンは「身近な家電」から「ちょっと贅沢な家電」に変わるかもしれません。
④冷媒ガス削減の国際的流れ
2027年基準強化の背景には、国際的な冷媒ガス(フロンガス)削減の流れもあります。
冷媒ガスはエアコンの冷暖房効率に直結しますが、地球温暖化に強い影響を及ぼすため、世界中で使用削減や置き換えが急速に進められています。
日本も国際的な合意や条約(モントリオール議定書・キガリ改正)に合わせて、冷媒の環境負荷を減らすための基準を強化しています。
今後は、省エネだけでなく、より環境に配慮した冷媒へのシフトも加速していくでしょう。
エアコン選びの際は、「冷媒ガスの種類」や「温暖化対策」も意識すると、より環境にやさしい選択ができますよ。
2027年以降のエアコン価格はどうなる?大幅値上げの理由
2027年以降のエアコン価格はどうなる?大幅値上げの理由についてご紹介します。
エアコンが今後どのように変化するのか、価格や家計への影響までしっかり見ていきましょう。
①コスト増加の背景
2027年以降、エアコンの値上げが避けられない一番の理由は「製造コストの大幅アップ」です。
新基準を満たすためには、高性能コンプレッサーや大型の熱交換器、断熱材の高品質化、AI制御など、従来モデル以上のパーツや技術が求められます。
さらに、製造ラインの改良や検査体制の強化といった工場面での追加投資も必要です。
このような技術革新と投資増加が、エアコンのコスト上昇に直結します。
メーカー各社も利益を確保するため、価格転嫁せざるを得ない状況にあるのです。
②どれくらい値上がりするのか
では、実際どれくらい値上がるのでしょうか?
現在、手ごろなモデルは5万円前後から購入可能ですが、2027年以降は「最低でも10万円前後」になるという予測が出ています。
さらに、世界的な物価上昇や資材高騰なども重なれば、1台あたり1.5万円~3万円、もしくはそれ以上の値上げも現実的と言われています。
とくに安価なベーシックモデルは市場から消えてしまう可能性が高いので、エアコンは「誰でも気軽に買える家電」から「高級家電」に近い存在へと変化するかもしれません。
この値上がり傾向は、しばらく続くことが予想されます。
③家計に与える影響
エアコンの値上がりは、家計へのダメージも無視できません。
例えば、家族用に複数台買い替える場合、従来なら20万円程度で済んでいたものが、30万円~40万円へと一気に跳ね上がる可能性もあります。
また、購入価格だけでなく、設置費用や工事費も同時に値上げされる傾向にあります。
こうした負担増を避けるためにも、早めの買い替えやキャンペーン活用など、計画的な行動が重要です。
将来的な出費を抑えるには、「今のうちに」対策しておくのが得策といえるでしょう。
④安いモデルが消える理由
新基準に適合しないモデルは、2027年以降「製造・販売禁止」となるため、今まで人気だった安価な機種は一掃される見通しです。
安さの秘密は、部品や設計の簡略化、省エネ性能より価格重視の仕様にありました。
しかし、APF基準が厳しくなれば、こうしたモデルは市場から姿を消します。
つまり、「今のうちに買っておけば安く済む」モデルは、2027年までの期間限定商品になるということです。
今後は「価格よりも省エネ・高性能」で選ぶ時代にシフトしていく流れとなります。
古いエアコンを使い続けるリスクとデメリット
古いエアコンを使い続けるリスクとデメリットについて解説します。
それでは、古いエアコンをそのまま使い続ける場合、どんなリスクがあるのか詳しくみていきましょう。
①電気代負担の増加
まず最大のデメリットは、電気代がどんどん高くなることです。
20年前の古いエアコンと、最新の省エネエアコンを比較すると、年間で1万円以上電気代が高くなるケースも少なくありません。
エアコンは使う頻度が高い家電なので、1日数時間の使用でも長い目でみると電気代に大きな差が出てきます。
しかも最近は電気料金の値上げも続いているので、古い機種を使い続けると「知らない間に家計を圧迫していた…」なんてことも起こりがちです。
省エネ基準が強化される今後は、こうした無駄な電気代をいかに減らすかが大切なポイントになります。
②故障や修理不可のリスク
エアコンは10年~15年が寿命とされていて、それを過ぎると故障のリスクが一気に高まります。
古いエアコンでは、冷えが悪い・異音がする・水漏れが起きるといったトラブルが増えがちです。
もし修理しようと思っても、古いモデルはすでに部品の製造が終わっている場合も多く、「修理不可」と言われてしまうことも…。
また、古いエアコンは修理しても再び故障しやすく、費用も新規購入より割高になるケースが少なくありません。
壊れる前の早めの買い替えが、結局いちばん経済的で安心な選択となります。
③部品供給や冷媒ガス問題
さらに、古いエアコンの場合、部品の調達や冷媒ガスの供給も大きな問題となってきます。
冷媒ガス(フロンガス)は、地球温暖化防止のために世界的に規制強化が進んでおり、古いタイプのガスはどんどん価格が高騰したり、入手困難になったりしています。
もし故障して冷媒ガスが必要になっても、すでに流通していない場合は「もう直せません」と言われてしまうことも増えています。
また、古いモデルは高い温室効果ガスを使っているため、環境負荷も大きいのが現実です。
結果として、古いエアコンを使い続けるほど不便やリスクが高まることを覚えておきましょう。
④賃貸住宅やオーナー側の注意点
賃貸住宅の場合、古いエアコンが故障したときはオーナー(大家さん)が対応するケースがほとんどです。
入居者から「冷えない」「壊れた」とクレームを受けたり、最悪の場合は家賃減額や契約解除につながることも…。
また、修理不可や部品調達不能となれば、オーナー側の急な出費やリスクも無視できません。
定期的なメンテナンスで延命も可能ですが、「製造から10年以上経ったエアコン」はクリーニング後も保証外となることが多く、あくまで応急措置です。
早めに買い替えることで、トラブルや余計なコストを未然に防ぐことが大切です。
エアコン買い替えはいつがベスト?賢い選び方とポイント
エアコン買い替えはいつがベスト?賢い選び方とポイントについて解説します。
ここでは、今後のエアコン選びで損しないためのタイミングやポイントについて、具体的に解説します。
①買い替えに最適なタイミング
エアコン買い替えのベストタイミングは、「2025年から2026年末まで」と言われています。
2027年が近づくと、駆け込み需要でエアコンの在庫が不足したり、設置工事が混み合って予約が取れないなど、混乱が予想されます。
人気モデルは早めに売り切れたり、価格も急騰しやすいため、「早めの計画」がとても重要です。
とくに10年以上使っている古いエアコンや、「冷えが悪い」「異音がする」「リモコンが効かない」などトラブルのある機種は、今のうちに買い替えを検討しましょう。
タイミングを逃さず動くことで、無駄な出費やストレスを減らせます。
②買い替え時に見るべきポイント
買い替え時に大事なのは「性能」と「使い勝手」をしっかりチェックすることです。
まず注目したいのは省エネ性能。APF(通年エネルギー消費効率)が高いモデルほど、電気代の節約になります。
また、冷暖房能力が部屋の広さに合っているか、静音性やフィルターの自動掃除機能があるかなど、生活スタイルに合った機能を選ぶのも大切です。
エアコンにはスマホ連携やAI制御など便利な最新機能も増えているので、予算と相談しながら選びましょう。
工事費やリサイクル料金などの「隠れコスト」も忘れずにチェックしてください。
③省エネマーク・APFの確認方法
エアコン選びでぜひ確認したいのが、「省エネマーク」と「APF(通年エネルギー消費効率)」です。
2027年以降は、省エネ基準をクリアしたモデルには「緑色マーク」、未達成のモデルには「オレンジ色マーク」が表示されます。
家電量販店やメーカーのカタログでも、APF値や年間消費電力量が必ず載っていますので、数字を見比べて選ぶと失敗がありません。
APFの数値が高いほど省エネで、電気代が安く済みます。
気になる機種があれば、APFや省エネマークを実際にチェックしてから購入しましょう。
④総コスト(本体+設置+ランニングコスト)で考える
エアコン選びでは「本体価格」だけでなく、「総コスト」で比較することが大切です。
本体の値段が安くても、設置工事費やリサイクル料金、そして毎月の電気代などランニングコストが高ければ、長い目で見て損するケースもあります。
購入前に、本体+設置+年間電気代などの合計コストをシミュレーションするのがおすすめです。
たとえば省エネモデルは初期費用が高くても、10年単位で考えれば電気代の節約分で元が取れることも多いです。
こうした「トータルでお得」な選択を心がけると、失敗がぐっと減りますよ。
エアコン2027年問題を乗り越えるために今できること
エアコン2027年問題を乗り越えるために今できることをまとめました。
「気づいた時には遅かった…」とならないためにも、今できることをひとつずつ実践していきましょう。
①早めの情報収集と計画
まず大切なのは、2027年問題の内容をしっかり理解し、早めに行動を計画することです。
新基準や今後の価格動向をニュースやメーカーサイトなどでこまめにチェックし、情報をアップデートしましょう。
特に買い替え予定がある場合は、2025~2026年に向けて必要な資金やモデル選び、設置業者の検討を始めておくと安心です。
「とりあえず様子見」で先送りにせず、タイミングを逃さない計画を立てておくことが後悔しないコツです。
早めに行動する人ほど、お得なキャンペーンや工事予約も取りやすくなります。
②定期的なメンテナンスで延命
まだ買い替え予定がない場合でも、定期的なメンテナンスを心がけることで、今使っているエアコンの寿命を少しでも伸ばすことができます。
フィルターの掃除や室外機の点検、プロによる分解クリーニングを利用することで、冷えや暖まりが悪い・異音などの不調を予防できます。
ただし、製造から10年以上経過したエアコンの場合は、クリーニング後でも故障や保証対象外となるリスクがあるので注意が必要です。
メンテナンスで延命できる間に、次の買い替えプランを練っておくのもおすすめです。
急な故障で慌てないためにも、定期的なケアを忘れずに続けましょう。
③古いエアコンの適切な処分
買い替え時や故障したエアコンは、正しい方法で処分することも大切です。
エアコンは家電リサイクル法の対象製品なので、必ず専門業者や購入店を通じてリサイクル回収を依頼しましょう。
自治体やメーカーによって処分費用が異なる場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
適切な処分をすることで、環境負荷を減らし、リサイクル資源の有効活用にも貢献できます。
自分で勝手に捨てたり、不法投棄は絶対にやめましょう。
④家計と環境にやさしい選択肢
新しいエアコンを選ぶ際は、「家計」と「環境」にやさしいモデルを選ぶことが重要です。
省エネ性能の高い機種を選べば、毎月の電気代がぐっと下がり、10年単位でみると大きな節約につながります。
また、最新の冷媒ガスや環境基準に適合したモデルは、温暖化対策や地球環境保護にも貢献します。
補助金や自治体の省エネ家電購入支援など、お得な制度も活用してみてください。
未来の暮らしと地球のために、賢い選択を心がけましょう。
まとめ|エアコン2027年問題とは生活と家計に直結する大きな変化
| 要点まとめ(詳細はページ内リンクから) |
|---|
| エアコン2027年問題の概要 |
| なぜ省エネ基準が改定されるのか |
| APFとは何か?その重要性 |
| 2050年カーボンニュートラルとの関係 |
エアコン2027年問題は、今まで普通に使えていたエアコンが、新しい省エネ基準によって一気に高性能化・高価格化するという、私たちの生活と家計に直結する大きな変化です。
この動きは、日本が世界と約束した「2050年カーボンニュートラル」に向けた環境政策の一環で、エアコンの消費電力や冷媒ガスの削減が強く求められています。
新基準の導入でメーカーは大幅なコスト増を余儀なくされ、手ごろな価格帯のモデルは市場から姿を消す見込みです。
結果として、2027年以降のエアコンは「高級家電」となり、買い替えや設置のタイミング、モデル選びが今まで以上に重要になります。
今使っているエアコンが古い場合は、早めに最新情報を集めて計画的な買い替えを検討することが、無駄な出費を防ぎ、快適な暮らしと環境への貢献につながります。